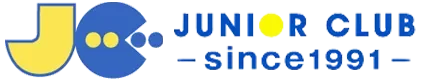小学校受験に関して保護者の方々が抱える疑問や情報に振り回される状況は、非常によく理解できます。特に「〇〇学校向き」といった言葉は、不安を煽りやすいものです。
保護者からよく聞く話の背景と、受験に臨む際の考え方についてお話します。
- 「あなたのお子様は〇〇学校向き」の根拠について
この表現は、多くの場合、以下の3つの要素に基づいています。
|
要素 |
根拠となるもの |
背景にある考え方 |
|
外部の評価 |
幼児教室の先生、知人の保護者、受験経験者などの主観的な意見や過去の経験。 |
「この子の得意な課題(例:指示行動が得意、運動が得意)は、あの学校の試験で高評価につながるだろう」という推測。 |
|
子どもの個性と雰囲気 |
子どもの持つ雰囲気、性格、集団での振る舞い、親子のやり取り。 |
自由で活発な子は「自由保育の学校向き」、落ち着いて指示が聞ける子は「伝統校・ペーパー重視校向き」といった類型化。 |
|
親の雰囲気 |
親の服装、話し方、教育方針、職業など。 |
伝統校は「保守的な雰囲気の親」、新しい学校は「先進的な教育に理解のある親」を求める傾向があるという経験則。 |
「学校向き」という言葉の真実
ご指摘の通り、「学校向き」とは、現在の試験の傾向や学校の雰囲気と、お子様とご家庭の現在の状態が合っているという意味合いが強いです。これは、お子様の将来や6年間の成長を保証するものではありません。
受験のプロはこの言葉を使うことで、「このタイプの学校を目指すなら、このような準備が必要だ」という具体的な対策を促しているケースもあります。
- 「普通に過ごして家庭生活がしっかりしている子」とは何か
学校の先生が求める「普通に過ごして家庭生活がしっかりしている子」とは、決して特別な英才教育を受けた子のことではありません。これは、試験や面接を通じて、以下の3つの力が身についているかを見ています。
① 基本的な生活習慣と自立心
- 自力でできる: 自分で身支度をする、脱いだものを畳む、排泄を済ませるといった生活の基本が確立していること。
- お手伝い: 家庭で役割(お手伝い)を持ち、人のために動く経験をしていること。
- 規則正しい生活: 早寝早起き、規則的な食事など、心身が安定したリズムで生活していること。
② 社会性と聞く力
- 挨拶・返事: 目を見て、はっきりとした声で挨拶・返事ができる。
- 指示の理解と実行: 先生の話を最後まで聞き、その指示やルールを理解して行動に移せること(ペーパーや行動観察の基礎力)。
- 集団での振る舞い: 順番を待つ、お友達と協力する、道具を大切に扱うといった社会的なマナーが身についていること。
③ 親子の安定した関係
- 豊かな対話: 親子の会話が多く、子どもが自分の考えや気持ちを言葉で表現できること。
- 自己肯定感: 親が子どもの頑張りやプロセスを認め、自分に自信を持っていること。
「普通に過ごす」とは、これら基本の生活習慣を親が丁寧に教え、子どもが愛情と規範の中で安定して成長している状態を指します。
- 保護者が情報に振り回されないために
小学校受験の情報過多の状況において、保護者の方向性を決めることが最も重要です。
保護者の視点で見極めるポイント
|
学校のタイプ |
向いている家庭の方針・環境 |
|
共学 |
多様性を尊重し、リーダーシップや協調性のバランスを重視する家庭。 |
|
男子校 |
個々の興味・関心を深く追求させたい、体力・精神的なタフさを求める家庭。 |
|
女子校 |
伝統や教養、きめ細やかな指導を重視し、思春期の同性とのびのびと過ごさせたい家庭。 |
|
附属校 |
受験のプレッシャーを避けて、大学までの一貫教育と様々な課外活動を経験させたい家庭。 |
|
進学校 |
高水準の教育を求め、子どもが知的好奇心旺盛で学習意欲が高いと考える家庭。 |
成功のための保護者の心得
- 「親の軸」を定める: 「わが子にどのような大人になってほしいか」という家庭の教育方針を夫婦で共有し、これをすべての情報取捨選択の基準とします。
- 学校を「わが子」の目で見る: 説明会や行事に足を運び、校長先生の言葉や在校生の雰囲気を、子どもの個性と照らし合わせて判断します。
- 情報源を絞る: 信頼できる幼児教室の先生や、特定の学校の情報を共有する少数のネットワークに絞り込み、不確かな情報に時間や労力を費やさないことが大切です。
ジュニアクラブでは、ご相談・面談をいつでも承っております。ちょっと聞きにくいけど…という事でもぜひご相談いただければと思います。
ジュニアクラブ恵比寿教室