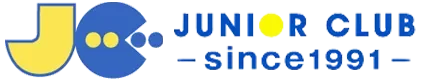慶應義塾幼稚舎と慶應義塾横浜初等部は、ともに慶應義塾の一貫教育を担う小学校ですが、その教育方針、入試内容、そして合格後の進路には明確な違いがあります。受験に臨むにあたっては、この違いを理解し、それぞれに合った心構えと準備をすることが重要です。
慶應幼稚舎と慶應横浜初等部の違い
1. 進路
- 慶應幼稚舎:卒業生は基本的に慶應義塾の中学校(慶應義塾普通部、慶應義塾中等部、慶應義塾湘南藤沢中等部)のいずれかに進学します。多くの生徒が慶應義塾普通部や慶應義塾中等部のある三田・日吉方面へ進みます。
- 横浜初等部:卒業生は原則として慶應義塾湘南藤沢中等部へ進学します。大学までの一貫教育を前提としており、湘南藤沢キャンパス(SFC)での教育が中心となります。
2. 教育方針・校風
- 慶應幼稚舎:創立者・福澤諭吉の「独立自尊」の精神を重んじ、6年間担任持ち上がり制で、学力だけでなく、人間性や社会性をじっくり育む教育を実践しています。伝統を重んじつつも、自由で活発な校風が特徴です。
- 横浜初等部:幼稚舎と同じく「独立自尊」を掲げながらも、SFCの理念である「問題発見・問題解決」能力の育成を重視しています。体験型教育や情報教育に力を入れており、より現代的な教育を志向していると言えます。
3. 入試内容
慶應幼稚舎:ペーパーテストは比較的少なく、行動観察、運動、絵画・制作などが重視されます。答えのない課題を通じて、子どもの個性、発想力、協調性を総合的に評価します。特に、所作や言葉遣い、先生や他の受験生とのコミュニケーション能力が非常に重要視されます。
横浜初等部:幼稚舎に比べてペーパーテストの比重が高いのが特徴です。推理・思考力や記憶力、指示を聞く力などが問われます。また、面接がない代わりに、願書に課題図書に関する感想などを記入する項目があります。運動能力や制作も評価されますが、論理的な思考力や知識を問う問題が多い傾向にあります。
受験に向けての心構えと準備
1. 共通の心構え
- 親の覚悟と信頼関係:最も重要なのは、親子で受験に臨むという覚悟と、子どもとの間に強固な信頼関係を築くことです。「何が正解かわからない」と言われる小学校受験だからこそ、親が焦らず、子どもを信じて見守る姿勢が大切です。
- 普段の生活態度:試験の場だけでなく、日頃から「独立自尊」の精神を育むことが重要です。挨拶や返事、物の貸し借り、整理整頓など、基本的な生活習慣を身につけ、自立心を促しましょう。
- 豊かな体験:自然に触れる、美術館に行く、様々な人と話すなど、実体験を多く積ませることが、発想力や表現力を豊かにします。
2. それぞれに向けた準備
- 慶應幼稚舎:
- 行動観察・運動:集団での活動で、他の子どもと協調し、自分の役割を果たす練習をしましょう。指示を最後まで聞き、俊敏に行動する力が求められます。
- 絵画・制作:ただ作るだけでなく、「なぜこれを作ったのか」「どんな工夫をしたか」を自分の言葉で説明できるように、日頃から問いかけ、子どもの考えを引き出す練習をしましょう。
- 対話力:試験官と笑顔で会話できる、自分の意見を相手に伝えられるようコミュニケーション能力を養いましょう。
- 横浜初等部:
- ペーパー対策:様々な種類のペーパー問題に触れ、指示を正確に理解し、最後までやり抜く集中力を養いましょう。推理や記憶、思考力を問う問題に特化した対策が必要です。
運動・制作:運動能力に加え、協調性や粘り強さが評価されます。制作では、指示された材料を無駄なく使うなど、課題を的確にこなす力が求められます。
~まとめ~
慶應義塾の小学校受験は、単なる知識や技術を問うものではなく、その子が持つ個性や人間性、そして慶應義塾の教育に馴染める資質があるかを総合的に見極めるものです。ジュニアクラブでは、お子さんの得意な部分を伸ばし、不足している部分を補うような準備を、日々の生活の中に取り入れていくことが成功の鍵となります。
ジュニアクラブ恵比寿教室